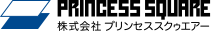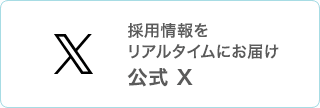祝日に思う事
2010年09月24日
今週は、敬老の日と秋分の日の祝日が重なり休みの多い一週間となりました。連休を多くするために作られたハッピーマンデー制度により敬老の日が9月の第3月曜日になったわけですが、私なんかは違和感を感じますね。私にとっては敬老の日は物心付いた時から9月15日と決まっていたわけで日付が決まっているほうが分かりやすかったように思います。慣れなのかもしれませんが国民の祝日はやはり日付で決めたほうが居住まいを正せるのではないでしょうか。体育の日なども東京オリンピック(戦後日本の復興のシンボル的存在であった)の開会式を祝日にしたんだからその起こりを大切にして10月10日から移すべきではなかったと思うのですが・・・・体育の日が10月第2月曜日・・・なんか力が抜けるのは歳を取った証拠なんでしょうか。
それはともかく、敬老の日と彼岸の入りが近い事もあり思い出すのが母方の祖母の事です。明治33年の生まれですから1900年生まれです。19世紀最後の年に生まれ92歳で亡くなりました。私は小さな頃から祖母の話しを聞くのが好きで、母が幼い頃の苦労話を良く聞きました。祖母は幼少の頃、実母(私にとっては曾祖母)を病で亡くしています。一人っ子だった祖母は父(曾祖父)との二人の生活になるのですが父親は昔気質の人で酒飲み、苦労したそうです。成人となり三味線を教えていた時(この辺の話が私が子供時代に聞いたのでよく理解できなかったのですが三味線を習っていたというのですから芸者だったのかもしれません)、出会った尺八と書道の先生と結婚します。二人の姉妹の母となり幸せの絶頂であった時、夫(祖父)をその当時流行した腸チフスであっけなく亡くします。まだ幼い二人の娘(当時7歳の伯母と4歳の母でした)を抱え、途方にくれた時期に重なるように戦争が始まります。幼い私はその頃の苦労話をふんふんとまるで物語を聞くように聞いていましたが社会人となり少ないながらも人生経験を積んでくるとわかる事があります。口では言えない苦労があったんだろうなと想像できます。当社では「シングルマザーのためのマンション講座」というサイトを運営していますが、現在のように女性の社会進出が可能な時期でも女性一人で子供を育てるのは大変で皆さん苦労されているのですから。
私はその祖母に大変可愛がられたのですが、その祖母の口癖が三つありました。
三つとは
「情けは人の為ならず、回りまわってわが身の得」
「なる堪忍誰もする。ならぬ堪忍するがまことの堪忍」
「顔の器量より心の器量、世間通じるどこまでも」
です。
三つ子の魂百までと言いますが幼少の時に繰り返し、繰り返し聴いたこの言葉は未だに心の底に残っているものです。特に二つ目の「堪忍」、これは我慢とは違うのです。我慢とは自分に生じた欲望や感情を抑える事ですが、堪忍とは人から受けた不条理な仕打ちや言動に対して生じた怒りを耐え忍ぶ事なんだと理解しています。「耐えられないような仕打ちを人から受けてもそれを耐え忍び相手を許す事が出来る事、それが本当の意味での堪忍なんだ」と。
人間は成長していく途中で色々な人の影響を受けていくものなんでしょうが祖母は私にとって大変大きな影響を与えた人でした。義理人情を大切にし、忠臣蔵をこよなく愛した男勝りの祖母。敬老の日と、忠臣蔵が話題に上る年末になると思い出します。
ありがとう。