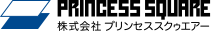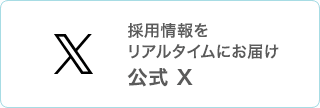江戸城の正門
2015年01月26日
いよいよ今年の東京マラソンまで一カ月を切りました。私にとってこの時期はとても憂鬱な時期でもあります。走り込みをしなければならない時ですから。前にも書きましたが30キロを一回、37キロを二回、マラソン大会の二週間前までに自分に課したノルマです。これができない限りマラソン大会に出場しないと決めています。例年、年に二回のフルマラソンを走っていたのですが昨年より年に一回にしました。当然、走り込みの回数も減り長距離を走ることに自信が持てなくなったせいか、一年ぶりに30キロを走るとなると緊張してしまいます。「果たして体が覚えているのか?」。自信がない中、先日自宅から皇居3週をして帰ってきました。何とか体は長距離走を覚えているようで最後までキロ5分のペースで走り切ることができました。少しホッとしました。
それはともかく、皇居を走っている途中に考えたのが「江戸城の正門はどこか?」なのです。今は皇居ですから皇居の正門は二重橋がある皇居正門です。しかし江戸城だったころの正門はと聞かれると普通に考えれば大手門ですよね。しかし、最近読んだ本では江戸城の正門は半蔵門だというのです。理由はいくつも書かれています。半蔵門を出た麹町あたりは旗本や譜代大名の屋敷が集中していたこと、古地図には半蔵門を正面にした地図が存在すること、現在の天皇陛下の外出はいつも半蔵門からであること等です。
確かに皇居の外周を反時計回りにジョギングしていると皇居外苑から大手門を通り平川門まではフラットな道なのですが、平川門から乾門までの道のりはキツイ上り坂が続きます。少し下った後、半蔵門までフラットな道となり半蔵門を超えて桜田門までは長い下りが続きます。桜田門から不浄の門とされる平川門までは低地であり、乾門から半蔵門が高地になっています。そう考えると半蔵門が表の玄関としての正門であるというのもうなずけるのです。
これが事実なのか、誤っているのか、分かりません。全体的なイメージとして西向きに表門を作るというのは何となく抵抗がありますし、半蔵門から始まる新宿通りが尾根道だということから半蔵門は有事の非常用脱出口だったのではないかとも思うのですが、真実は作ったものでなければわかりません。どう解釈するか自由なのですからあれこれ想像しながら走ると楽しいものです。「松の廊下で刃傷沙汰を起こした浅野内匠頭は江戸城から出された時に使われた門がこれか」「何で和気清麻呂の銅像があるのだろう」興味は尽きませんね。色々なことを考えながら走るのは楽しいですよ。
死を覚悟して紛争地に行き人質になった人を助けるというなら、その前に日本国土にいて何の罪もない少女たちを誘拐、拉致された人を助けることを最優先にすべきだと思いますが、どうなのでしょう。