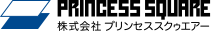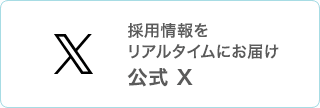儒教という宗教
2014年05月19日
私は脩己治人(自分自身を修養して徳を積み、その徳で人を収めていくこと)の学問として、「大学」や「論語」、「中庸」「孝経」などを勉強し、また講習会にも参加してきました。そして学びながら思うことですが「大学」は別として、その他の書物は比較的わかりやすい文章もあれば、現代訳を読んでも意味が分からない難解な文章も出てきます。「論語」などは、ある章では否定していることを他の章では肯定している場面があったり、聖人君子としての顔を持つ孔子の言葉があると思えば、とても人間臭さが感じられる孔子の言葉があったりと宗教としてのバイブルには少し物足りなさを感じていました。
そんな中、最近ある人の勧めで浅野裕一さんの「儒教 ルサンチマンの宗教」という本を読みました。この本は今から15年前に出された本ですから読まれた方もいらっしゃるでしょうが、まあ、孔子を含めた儒教を徹底的に批判しています。
ルサンチマンとは、弱者の怨念や憎悪の感情のことを指す哲学用語です。孔子は仕官を求めて弟子をつれ諸国を流浪するのですが、どの国王にも認められず結局、不遇の中で人生を閉じることになります。誰にも認められることなく失意の連続の中での悔しさや無念さが儒教を生み出したというのです。「論語」に限らず孔子はその当時(紀元前500年頃)の周の国の礼や、そこから遡ること1000年前に出来たとされる夏の国や500年前の殷の国の礼を知り尽くしていたということになっていますが、この本ではそんなことはありえないことで孔子は口から出まかせを言っていたと結論付けています。孔子は身分の低い階級に生まれているので当時の周の礼さえ知っている立場にいるはずがなくまたそれを知りえる職業に就いた形跡もないといいます。孔子の死後、儒教を引き継いだ学者たちが孔子を神格化するために後から作った話によって孔子がさも礼を学んだことあるように事実を作り替えたとも。
何とも衝撃的な本です。儒教をこき下ろした本なのですが、儒教を少しかじった私にとっては何とも腑に落ちてしまいました。色々な場面で「なぜこんな話が出てくるんだ?」「こんな嫉妬じみたことを君子が言うのか?」など「論語」などは度々出てきます。また一例をあげると礼に詳しいはずの孔子が大廟で周りの人に廟での礼の仕方を聞くシーンがあります。そこで周りの人が「孔子は身分が卑しい出なのに礼を知っているといっているがやっぱり人に聞いているじゃないか。(ということは礼を知らないんだ。)」と揶揄されます。それに対して孔子は「それが礼だ」というのです。人の顔を立てるという意味で私は解釈していたのですがこの本の考え方からするとこの返答は苦し紛れの言い訳になります。そしてそのほうが素直な解釈になるような気がします。体系立てて書かれている本を除き「論語」を全体的に理解するには「ルサンチマンの宗教」と考えて読むと非常にわかりやすくなると思います。孔子を儒教の教祖として究極の君子と考えるよりは人間「孔子」と考えるほうがより近く四書五経を読める気がします。
論語を読もうとされる方は「ルサンチマンの宗教 儒教」を読まれることをお勧めします。

儒教 ルサンチマンの宗教(浅野裕一著・平凡社新書)