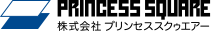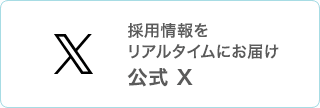ムラ社会の原型
2014年01月30日
先日、顧問の先生より戴いた本を読みました。『「近世百姓の底力」村から見た江戸時代』という題の本です。私は良く書店には顔を出す方ですが、どうしても目に留まるものは推理小説や経済小説、歴史小説では時代の変わり目の話であり、この題名の本は書店では決して手に取らない本です。人から勧められた本は読んでみるべきです。大変、面白くまた我々日本人の原点が知り得て勉強になりました。
私たちもよく時代劇を見ますが時代劇の舞台になっているのは江戸の町であり、あまり農村を舞台にしていません。しかし、たまに見かけても村の仕組みまで踏み込んだものはなく農村には庄屋さんと百姓、水飲み百姓がいる位しか知識がありませんでした。
この著書は、江戸中期から後期にかけて千葉県茂原市を舞台にした百姓たちの生き方、考え方を当時の文献をもとにして講義という形で書かれています。読んでいくにつれ、私がいかに日本の農家について、村について無知であったかが露呈しました。
そもそも、大抵の百姓にも苗字があったことすら知りませんでした。公の場では名乗れないだけで苗字自体はあったのです。私は今まで明治になって平民が苗字をつけることを義務化してから名乗ったとばかり思っていました。また、農家の家を継ぐという事は我々が考える跡継ぎの考え方とは全く違い、大変に重要なことで、その後継ぎとなった人は親の名前を継ぎ、名前が変わったのです。その家の当主が権左衛門とすると、後を継ぐ息子は家督を相続した時点で何代目権左衛門となり、家を継いでいったのです。今の歌舞伎役者や落語家の襲名のようですね。家がいかに大事な存在であったか、またそれを代々引き継いでいくことが子孫の大切な使命であったか改めて教えて頂きました。
また、数十軒家が集まりそこで村が構成されます。その村の役割は現代の社会ではあまり存在しないほど強いものです。村は最小単位の行政組織であり、その組織の運営には庄屋と呼ばれる村の長、その下に組頭、百姓代という三者で行われていましたが、その自治の範囲が想像以上に広範囲なんです。冠婚葬祭はもちろんの事、田畑の農作業の協力から、個人的な借金や百姓間でのもめ事までも、五人組、それで解決出来なければ村で解決します。
現代に置き換えれば、職場も一緒、日々の生活も一緒、争い事や一身上の都合も全部オープンになる集団生活のようなものです。現代のように農作業機械がない時代、農業で生計を立てるためはこのような集団生活は必要不可欠な手段だったのでしょう。
この様な村の生活は、社会生活と家庭生活が離れている生活に慣れた我々にとっては、そのような集団生活はかなり窮屈に感じてしまいます。しかし、オウム真理教のように社会にテロ攻撃をするような集団が今でも無くなることなく集団生活をしているのを聞くにつけ、決して欠点ばかりでもないのでしょう。人と人との繋がりがともすれば希薄になり、人と協力し合って生きていくことに下手な現代人にとっては我々祖先の共に助け合ってきた生き方を知っておくことは必要なことです。
しかし、村人同士のお金の貸し借りが基本無利子とは。。。さすが、日本です。